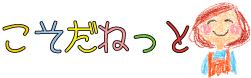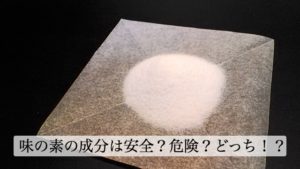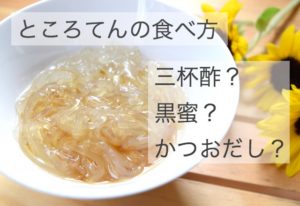赤ちゃんが寝ている時に、よだれが多く感じた事ありませんか?
お昼寝から起きると、お洋服がよだれでグショグショで、「この赤ちゃん大丈夫かしら、、、。」なんて心配した事ないですか?
赤ちゃんによっては、よだれの出ない赤ちゃんもいたりして、ママ友同士で話していると不安になりますね。
今回は、赤ちゃんが寝ている時のよだれについてお話ししましょう。
目次
赤ちゃんのよだれは悪いものではない
まず、赤ちゃんのよだれについて、お話しましょう。
まず、よだれ自体は、決して悪い物ではありません。
大人でもそうですが、よだれ(唾液)は消毒の効果があります。
よく、動物が傷を舐めて治したりしてますよね。
たまに「傷にツバをかけておけば治る」なんて言ってる人もいるくらいですから。
赤ちゃんであれば、よだれが多ければ虫歯予防になります。
それから、よだれ(唾液)は消化酵素が含まれていますので、食物を上手に消化して体に無理なく取り込む事ができます。
昔から、「よだれの多い赤ちゃんは、胃が丈夫」だと言われていますね。
そんな訳で、赤ちゃんのよだれ自体は悪い物ではありません。
では、なぜ?赤ちゃんはよだれが多いのでしょうか?
一つは、歯が生え始めてきて痒いからと言うのが大きな理由です。
その他に、口の機能が整っていなくて、上手く唾液を飲み込めないと言う事もあります。
一般的に、赤ちゃんはよだれが多いのが普通です。
病気が原因のよだれもあります
例えば口の中に出来物ができている時もよだれが多くなります。
赤ちゃんの口の中に口内炎などのできものができると、やはり気になるため、どうしてもよだれが多くなります。
また、赤ちゃんだって口内炎は痛むので、機嫌が悪くなったり、ミルクを受け付けなくなることもあります。
ですので、赤ちゃんがよだれをたくさん出ていて機嫌が悪かったりミルクを嫌がるなどする時は口の中を覗き込んでみてください。
口の中になにか病気が見つかるかもしれません。
病気ではなく口呼吸が多くなっていてよだれが出ている場合もあります。
赤ちゃんの鼻水を放置しているたりすると、鼻呼吸が苦しくなります。
そして、次第に口呼吸の癖がついてしまうことがあります。
口呼吸そのものが病気というわけではありませんができれば鼻呼吸を習慣にしたいものです。
口呼吸の赤ちゃんは、口をいつも開けているので口が乾かないように、体がよだれの分泌を多くするように働きます。
口呼吸をよくする子供になると異物を含んだ外気が直接のどへと入り込むため、細菌などのウイルスが取り込まれやすくなってしまいます。
こういったケースもありますので、あきらかにいつもと違うと感じたら、検診を待たずにかかりつけの小児科医にご相談していただく事をおススメします。
赤ちゃんが寝ている時によだれが多いのはうまくよだれを飲み込む事が出来ないから
さて、赤ちゃんのよだれは、心配ない事を理解していただいたところで、寝ている時によだれが多いのは?問題ないの?と思いますね。
これも、いままでの話とほとんど同じで、心配はないものの方が多いです。
なぜなら、赤ちゃんの口の機能は、まだ大人と同じ様に整っていないからです。
大人であれば、寝ている時は大抵、自然とよだれを飲み込んでいると思いますが、赤ちゃんは口の機能や色々な面で未発達の為、うまくよだれを飲み込む事が出来ないのです。
なので、いくら問題ないといっても、喉をつまらせて「ゴホゴホ」いっているのは問題ですし、危険です。
ですので、寝せる時は横向きにしてあげたり、喉を詰まらせない様に、離乳食を食べた後、すぐ寝かせたりするのは避けた方が良さそうです。
とりあえずは、機嫌が良くていつもと様子が変わらなければ心配はいりません。
ただし、逆によだれが少なく、おしっこの回数が少ないときは、脱水症状も疑われます。
様子がいつもと違うと感じた時は、かかりつけ医に相談してみてください。
よだれかぶれの原因はよだれに含まれる成分
よだれかぶれとは、よだれが原因でなる皮膚炎の一種です。
生後3ヶ月後に増えるよだれで、口の周辺の皮膚に炎症を起こし、かゆみと湿疹がでます。
そもそも、よだれが原因というのに個人的には不思議に思いました。
よだれは自身の体内から出てくるのに、それが刺激で皮膚炎になるのが不思議でした。
よだれの99%以上が水分です。
しかし、そのほかに消化酵素や、抗菌物質、有機および無機成分、塩分などが含まれているのです。
これらは、口内を守る物質です。
口になんでもいれる乳幼児にとって、抗菌作用になります。
また、歯がはえると歯科予防にもなります。
しかし、一旦口からよだれとして出て、皮膚に触れると炎症します。
よだれに含まれる消化酵素は皮膚にとって負担になってしまうのです。
特に、乳幼児の皮膚は非常に敏感肌で、大人の半分の厚さしかないのも原因の1つです。
また、よだれでやわらかくなった皮膚を強い刺激でゴシゴシとふき取ると、皮膚に傷がつき、そこから炎症する恐れもあります。
よだれかぶれの予防法はとにかくよだれをふき取ること
よだれは、生後3ヶ月ごろから増え始め、1~2歳ごろには落ち着きます。
このよだれが出る時期は、以下のような原因でよだれが増えはじめます。
- 歯が生え始める
- 指しゃぶりをする
- なんでもものを口に入れてる
- 離乳食が始まる
- 声を出しはじめる
- 唾液がうまく飲み込めない
- あごの筋肉が弱い
- あごの骨が完成していない
など
特に、離乳食を食べ始めたころは、口内の唾液が増え、よだれも増えます。
そのよだれには、口内にのこった食べ物と消化物質などが含まれております。
口の中をきれいにするということも含め、白湯などをのんで口の中も清潔にすることをおすすめします。
また、皮膚が弱いので、ゴシゴシと荒い布で顔を拭いてはいけません。
できれば、コットンなど肌にやさしいガーゼをよく濡らしてしぼり、トントンと軽く押すような形でふき取りましょう。
最近のスタイ(よだれかけ)はかわいいものがありますが、こちらも気をつけなければいけません。
1日5~6枚ほど取り替える習慣をつけてください。
取り替えないと、洋服まで濡れて、首元までも荒れてしまうこともあります。
(ちなみに、寝かしつけの場合は窒息をしないよう、スタイはとってくださいね。)
よだれかぶれを予防するには、「皮膚についたままにしない」「やさしくふき取る」というのが1番です。
かぶれてしまった時の対策
予防をしても乾燥の強い時期は、かぶれてしまうこともあるでしょう。
そんなときは、口の周りを優しく洗った後、きれいな皮膚を保湿しましょう。
馬油やワセリンなどがおすすめです。
まだ乳幼児ですので、口に入っても安全なものを選びましょう。
わが子の場合、お風呂上り後、いつも身体全体をベビーマッサージで保湿していました。
その延長のように、顔もベビー用オーガニッククリームで塗っていました。
それでもかぶれてしまった時は、かぶれてしまった箇所を「トントン」と拭きながら保湿してあげてください。
かぶれてしまった場合はこれを数時間ごとに繰り返すことが大切です。
皮膚に水分が付いたままというのは、よだれに限らず皮膚を乾燥させます。
しっかり拭き取り、保湿をしてあげてださい。
赤ちゃんの新陳代謝は、とても活発なので1週間もすれば皮膚の回復が見られるでしょう。
しかし、かぶれがジュクジュクしたものや、1週間たっても直らないときは、皮膚科へ相談することをお勧めします。
医師の判断でステロイドの塗り薬を出されることがあるかもしれません。
通常、乳幼児用のステロイドはとても弱いものなので、副作用はそれほど心配することではありません。
心配であればとにかく、医師に質問や相談をすることです。
関連記事赤ちゃん用おすすめ保湿剤一覧!フケや乾燥肌にも効く保湿剤はこれ
関連記事赤ちゃんの唇が切れる!出血しやすい唇を冬の乾燥から守るには?
赤ちゃんのよだれかぶれまとめ
赤ちゃんのよだれは、生後3ヶ月ごろから増え始めて、1~2歳ごろには落ち着きます。
赤ちゃんのよだれが多いこと自体は問題ではありませんが、口の中の病気の可能性もありますので、あまりによだれが多いようであれば口の中を見てげてください。
また、よだれが原因で口の周りがかぶれてしまうこともあるので、細目によだれを拭いてあげてください。
色々な面で、他の子と違ったりすると心配になりますね。
いつもと同じで機嫌がよければ特に心配はいりませんので、安心して子育てしてください。