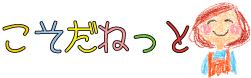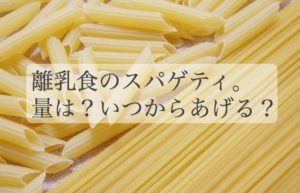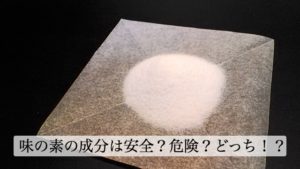7月の祝日である"海の日"って何をお祝いしている日なのだろうか?
あなたも一度は海の日の由来を疑問に思ったことがあるかもしれませんね。
今日は、そんな海の日についてのお話です。
明治天皇と海の日
明治9年(1876年) 明治天皇は五十日をかけて
東北地方・北海道を巡幸されました。
※巡幸(じゅんこう)とは、天皇が各地を見て回ることです。
青森から函館を経由して横浜港に到着した日が7月20日でした。
この日は長い間「海の記念日」と呼ばれていたそうです。
そしてこの巡幸では、初めて軍艦以外の船が使用されたそうです。
その時使用された船は、灯台巡視船で明治丸といいます。
この明治丸は、日本最古の鉄船でした。
船では初めて国の重要文化財に指定されています。
明治丸は東京海洋大学に保存されていています。
大規模な改修工事が行われて一般公開も行われているそうです
「海の記念日」から「海の日」へ
そんな長い間"海の記念日"と呼ばれていた7月20日ですが、
「海の恩恵に感謝して、海洋国家日本の繁栄を祝う日」として、
平成7年(1996年)の法改正で『海の日』と制定されました。
その後、ハッピーマンデー制度が導入されて、
海の日は、本来の7月20日ではなく、7月の第3月曜日になったのです。
※ハッピーマンデー制度とは、3連休を増やすために、
一部の祝日を特定の月曜日に移動させる制度の事です。
海の日がある7月を、国土交通省海事局では海の月間としていて、
国民に海の事を広く理解してもらうことを目的にしています。
そんな海の日ですが、現在のハッピーマンデー制度を
廃止にしましょうという働きがあるそうです。
近いうちに、海の日は本来の7月20日に戻るかもしれませんね。
3連休がなくなってしまうのは、個人的には少し残念な気もしますが、
本来の意味を考えると、戻す方がいいのかなと思ってしまいますね。
海の祝日があるのは世界で日本だけ
また、海の日を国民の祝日にしているのは、
日本しかないと言われているそうです。
日本は海に囲まれた島国です。
そんな島国の日本だからこそできた祝日なのかもしれませんね。
しかし海に囲まれた日本といっても、
47都道府県の中には海に隣接していない県もあります。
その中で、奈良県では7月の第3月曜日を
「奈良県 山の日川の日」と市の条例で決めているそうです。
今後は8月に「山の日」も新たにできるそうなので、
市の条例が変わるのか気になりますね。
山の日という祝日ができると、とうとう6月だけが祝日のない月になります。
今後、6月にも祝日ができるのか、非常に興味が湧きますね。
(締めくくりで脱線してしまった・・・笑)