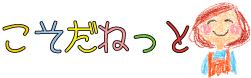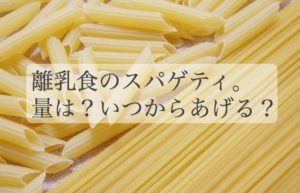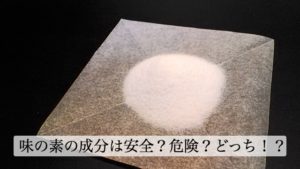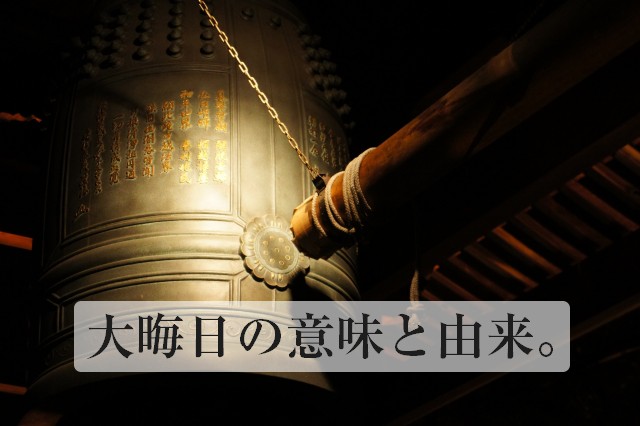
いよいよ12月に入ると、忙しいですね。
師走と書いて「しわす」と読みます。
師走の意味は、「先生(師)も走る」くらい忙しいという事です。
さて、今回は大晦日の意味と由来について、簡単にお話をしていきましょう。
大晦日の意味と由来
大晦日(おおみそか)とは、一年の最後の日の事をいいます。
三十日は、(みそか)と読みます。
よく、三十路(みそじ)っていいますよね。
あの、三十(みそ)です。
あの、三十(みそ)に日にちと書いて、三十日(みそか)です。
なので晦日は毎月体験していることになります。
年末の12月30日だけを指して、晦日と呼んでいるわけではありません。
ちなみに31日がない月は30日だったり2月だったりすると28日だったりとその月の最後の日が晦日になります。
そして一年の最後の三十日(みそか)だから(おおみそか)になるわけです。
除夜の鐘が108回の意味
大晦日の夜は、除夜と呼ばれていますが、年神様を迎えるにあたり、夜通し起きていました。
つまり、夜を除く→眠らない夜という意味です。
因みに、除夜に眠ると皺ができるとか、白髪になるとかの言い伝えがあります。
昔は、1日の始まりが夜に始まった、と考えられていました。
ですから大晦日の夜は、新しい年のはじまりでした。
地域によっては、ご馳走を大晦日に食べる所もあります。
除夜の鐘は、108回鳴らします。
元々は、毎月の月末に鳴らしていたそうですが、だんだんと大晦日に鳴らす様になりました。
因みに、108という数字は、仏教思想に基づいています。
108の煩悩(ぼんのう→心を惑わす、悩ませる、事です。)からきています。
つまり、108の悩みを、鐘を108回鳴らす事によって、この煩悩をとり除く事ができると言われています。
そして、澄み渡る心で、新しい年を迎えようという事です。
除夜の鐘の107回は、31日中について、最後の1回は年が明けてからつきます。
そうする事で、煩悩に惑わされなくなるようにという願いが込められています。
年越しそばの由来
さて、年末といえば、年越しそばですね。
年越しそばの由来も、お話ししましょう。
昔の江戸時代の商家は、月末は忙しかったといいます。
そこで、夜遅くまで仕事をしていて、夜遅くにお蕎麦を食べていたといいます。
なので、年越しそばは、その一年の最後のそばという意味です。
そばは、長く伸びる事から、「寿命が延びる」といわれています。
また、金細工の散らばった金のクズを集めるのに、そば粉を練った物を使ったという事から、縁起物としてそばを食べるという説もあります。
晦日に関する雑学
ちなみに晦日には、「暗い」という意味もあります。
昔の人のカレンダーは(江戸時代まで)月の満ち欠けに連動していました。
月末は、月が新月になって隠れてしまって見えないので、それにちなんで「暗い」という意味のある「晦」という文字が使われるようになりました。
最近は本屋さんでも時々見かけますが、月の満ち欠けと連動しているカレンダーってわかりやすくっていいいですね。
ちなみに、現在のカレンダーはグレゴリオ暦と言います。
昔の人のカレンダーは太陽太陰暦といい、月の満ち欠けと連動しています。
昔のカレンダーは太陽太陰暦と言って、一般に旧暦と言われているものです。
江戸時代までは太陽太陰暦を使っていました。
今の様なグレゴリオ暦になったのは明治5年の改訂からです。
それまでの太陽太陰暦は月の満ち欠けと連動していました。
例えば、1日は新月で月が見えません。
それから、徐々に月が見えてきて、15日に満月になる様になっていました。
それから徐々に月が欠けて、月末には月が新月になるので見えなくなります。
明治5年に明治政府は、西洋と統一しようとカレンダーも西洋が使っているグレオリオ暦を取り入れました。
しかも、準備期間は一ヶ月もほとんどない状態だったと言われています。
取り入れた当時は大変混乱した模様です。
ちなみに、旧暦の明治5年11月に発表し、旧暦の12月3日に取り入れたと言われています。
つまり、旧暦の明治5年12月3日が、いきなりグレゴリオ暦の明治6年1月1日になったわけです。
大晦日の意味と由来
- 大晦日は、旧暦の12月30日の事
- 除夜の鐘は、煩悩を消すため108回鳴る
- 年越しそばは、江戸時代の商家のなごり
大晦日が12月31日であったことを知っていた人は多かったと思いますが、晦日は毎月ありました。
除夜の鐘の意味や仕組みが分かると大晦日の過ごし方も変わってくるかもしれませんね。
昔の人は、月の満ち欠けで畑の種まきや、その他色々な事を決めていたということですから自然の理にかなったカレンダーでした。
もちろん月の満ち欠けって大潮とも連動してますから、漁の仕事にも随分役に立ったと思われます。
ついでにいうと、人間も月の満ち欠けの影響を受けているっていいますから、
人間本来の生活をしようと思ったら、太陽太陰暦のカレンダーがいいのかもしれませんね。
来年のカレンダーは月の満ち欠けカレンダーも買ってみようと思っています。
それでは、よいお年をお迎えください。