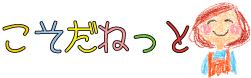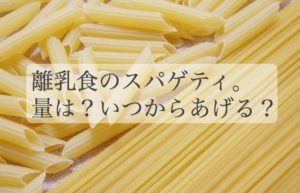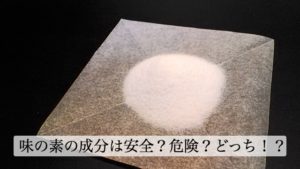敬老の日とは、「長年にわたり、社会に貢献してきた老人を敬い、長寿をお祝いする」という趣旨で始まった祝日です。
敬老の日は、平成15年(別名ハッピーマンデー)の祝日法改正より9月第三月曜日に決まっています。
平成14年以前は、9月15日に固定されていました。
という事で、2023年の敬老の日は、9月16日(月)になります。
敬老の日の由来は諸説ありますが、昭和22年9月15日兵庫県多可郡野間谷村で敬老会を開かれたのが始まりとされています。
敬老の日、孫からのおすすめプレゼント
- 似顔絵
- 手紙
- 手作りのフォトアルバム
- 写真+手作りフォトフレーム
- 手形足形(手形アートでも)
- 手作りお菓子
- 手作りのペン立て、メガネ立て
- 手作り小物
- 肩たたき券
- お手伝い券
おじいちゃんおばあちゃんは、お孫さんからの手作りプレゼントが何より嬉しいもの。
その中でも特に喜ばれる「孫の手作りプレゼントランキング」をご紹介します。
孫の描いてくれた似顔絵は、おじいちゃんおばあちゃんにとって大切な宝物となりますのでおすすめです。
手紙は少々難易度高いかもしれませんが、上手な文章である必要はありません。
おじいちゃんおばあちゃんに日々の感謝の気持ちを記しましょう。
手紙はどんなにつたない文章でも気持ちが伝わるから最高に嬉しいプレゼントです。
手作りのフォトアルバムは孫の成長がプレゼントになります。
コメント入りなら何度でも眺めてしまうはずです。
写真+手作りフォトフレームは、手作りのフォトフレームなら温かみがあっておすすめです。
手形足形(手形アートでも)は、絵が描けなくても大丈夫です。
手形足形を押して一言添えれば素敵なプレゼントになります。
手作りお菓子は、おはぎ、芋ようかんなどお年寄りに喜ばれる和菓子を選ぶのがおすすめです。
手作りのペン立て、メガネ立ては、牛乳パックを適当な長さに切って、布や折り紙などでデコレーションすれば立派なペン立てになります。
手作り小物は、しおり・キーホルダー・うちわなどがおすすめです。
しおりは、写真で作っても、絵を描いてもよいです。本を読むのが楽しみになるはずです。
キーホルダーは、孫の絵で作られた世界でたった一つのオリジナルです。
うちわは、孫の絵や手形、メッセージ付きなら使わずに飾ってしまうかもしれません。
肩たたき券は、敬老の日の定番プレゼントですが、今でも孫からのプレゼントとしてはおすすめです。
お手伝い券も、おじいちゃんおばあちゃん喜ぶと思います。
お手伝い券があれば、堂々とお手伝いを頼めますし、孫に会う口実も作れます。
以上、敬老の日の孫からのおすすめプレゼントでした。
孫からの手作りプレゼントなら、おじいちゃんおばあちゃんは何だって喜んでくれます。
心を込めて準備した孫からの手作りプレゼント。
贈るときに、ちょっとしたサプライズがあれば、家族みんなで楽しいひとときを過ごすことができますね。
おじいちゃんおばあちゃんが遠くてなかなか会いに行けないときは?
おじいちゃんおばあちゃんが遠くに住んでいて、なかなか会いに行けない。
そんなときは、手作りプレゼントにプラスして、写真やビデオでお孫さんの様子を知らせてあげましょう。
遠いからこそお孫さんの成長が伝わるようなプレゼントだとおじいちゃんおばあちゃんは喜んでくれるでしょう。
似顔絵や手紙などに、ビデオレターやボイスレター、動画DVDを添えるとお孫さんの成長を感じることができます。
遠くて一緒に過ごすことはできないけれど、「手紙を朗読」、「歌やミニ演奏会」、「劇の発表」などを撮影して送ることもできます。
これなら遠く離れていても、敬老の日をお祝いする気持ちが伝わります。
でも、どうしても忙しくてプレゼントや手紙が間に合わない。
そんな時は、メールや電話だってお孫さんとの大切なふれあいの一つとなります。
孫からメールや電話をもらえば、おじいちゃんおばあちゃんはその気持ちが嬉しいものです。
敬老の日をちょっと楽しくするポイント
敬老の日をおじいちゃんおばあちゃんと楽しく過ごすのに、大がかりな準備をする必要はありません。
ちょっとした工夫をするだけで、心に残る1日となります。
敬老の日をちょっと楽しくするポイントを3点紹介します。
一つ目のポイントは、手紙の朗読です。
敬老の日のプレゼントを渡す前に、準備しておいた手紙を朗読すれば、おじいちゃんおばあちゃんの喜びも更に大きくなります。
小さなお子さんなら、短いメッセージでも全然大丈夫です。
二つ目のポイントは、歌を歌うことです。
皆が知っているような童謡、秋にちなんだ歌を選ぶのがおすすめです。
例えば、「ふるさと」、「もみじ」、「まっかな秋」なら誰でも耳にしたことがありますよね。
皆で声を合わせて歌えば、自然と心も一つになります。
メロディーをリコーダーやピアニカ、カスタネットやタンバリンでリズムをとって、ミニ演奏会にしても素敵です。
三つ目のポイントは、劇を発表することです。
皆が知っている昔話や、ちょっとしたストーリーを自分たちで考えて、劇をするのも楽しいです。
役になりきってしまえば、おじいちゃんおばあちゃんも盛り上がること間違いありません。
その他にも、けん玉やお手玉、ビー玉で一緒に遊んだり、手遊び歌の「ずいずいずっころばし」や「おちゃらかほい」なども、お孫さんとの楽しいふれあいのひとときとなります。
敬老の日プレゼントまとめ
敬老の日のお祝い、何をプレゼントすればいいのかどうしても迷ってしまいますよね。
でも、物ではなく気持ちが嬉しいと感じているおじいちゃんおばあちゃん。
おじいちゃんおばあちゃんが近居、もしくは同居であれば敬老の日に一緒にお家に家族で出かけてもよいですね。
その逆で、おじいちゃんおばあちゃんをお家へ招待してもいいです。
「おじいちゃんありがとう!」、「おばあちゃん大好き」の気持ちをお子さんと一緒にプレゼントに込めれば、きっと喜んでもらえます。
そして何よりもお孫さんの成長や、一緒に過ごす時間こそが敬老の日のお祝いであり、プレゼントになります。
敬老の日が皆さんにとって、温かく楽しいひとときとなりますように。