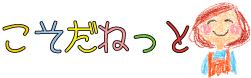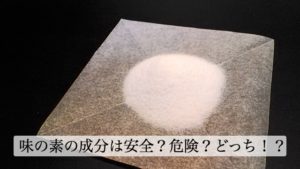ここ最近では、核家族化が浸透しているため都市部になればなるほどマンション住まいの家庭が多いですよね。
なので、昔よく目にしたこどもの日恒例の広い庭に空高くそびえ立つ鯉のぼりや武将がかぶっていたような本物そっくりの立派なカブトなどこのような飾り物を掲げて大々的にこどもの日を祝う家族が少なってきています。
その代わりにそれらの飾り物をコンパクトサイズにして、その代わりプレゼントや外食で補う形が主流となっているという話を聞きました。
個人的には「なんか昔と違うな~それでいいの?」、とか「こどもの日のプレゼントって?どんなものをあげているの?」など、ちょっと信じられない!という気持ちに包まれています。
しかし、最近のこどもの日はどこもはそうなんですって。
そこで今日は、こどもの日にプレゼントするその内容やプレゼントをあげるメリットなどを調べまとめてみました!
こどもの日のプレゼントは12歳ごろまで
子供(男の子)の成長を願うことから始まった端午の節句(こどもの日)ですが、最近ではお祝いにプレゼントをあげるのが本格化してきています。
こどもの日にプレゼントに何歳までプレゼントをあげるのかの正確な決まりはありませんが、12歳ごろまで(小学校卒業まで)という家庭が多いようです。
プレゼントされる側の子供たちにとってみれば、何歳になってもプレゼントは嬉しいものですよね。
もしかしたら、今もらったプレゼントがこどもの日のお祝いだなんてことすっかり忘れてしまっているかもしれません。
親にとっては、「大切なこどもの日だから、お祝いとしてプレゼントを贈る」わけなので、そのことは子どもたちにしっかりと伝えたいものですね。
良い機会なので、われわれ大人も、もう一度「こどもの日」について復習しておくとしましょう。
子供の日とは、1980年代に端午の節句、今ではこどもの日が主流になります。
昔は、子供が生まれてもなかなか育つ事が難しかったので、子供の日に「子供の成長を祝う+更なる成長を願う」ことから始まりました。
元気に育つ願掛けとして、吹き流しやしょうぶ湯が登場しました。
吹き流しは魔除け、しょうぶ湯も魔除けでしたり風邪をひかないようにと言う意味です。
カブト、太刀、太鼓は男の子の節句のためです。
子供の日の起源だった時代は武士が主流の時代なので男の象徴とも言えるアイテムを飾って成長を願いました。
健やかに育ってくれてありがとう!これからも元気に育ってほしい!
われわれ大人たちは、こどもの日の本来の意味をプレゼントと一緒に子供に伝える事が大切ですね。
こどもの日の人気プレゼントはレゴ
こどもの日のプレゼントは、コンパクトな飾り物を選ぶことによって金額的に抑えられる事と、祖父母が孫に会う口実にもなります。
こどもの日のプレゼントで人気なのはレゴです。
レゴは昔から人気のテッパン知育玩具ですね。
他にはゲーム・洋服・文房具などもこどもの日のプレゼントとして人気がありますね。
こどもの日の由来
「子どもの日」は、「端午(たんご)の節句」とも言います。
「端午(たんご)」とは、「月の端(はじめ)の午(うま)の日」という意味です。
「午」=「五」という語呂合わせで、5月5日を、「端午の節句」と呼ぶようになったのがこどもの日の由来です。
昔、中国では旧暦の5月に病気が流行り亡くなる人も多かったそうです。
このことから、5月5日の端午の節句には、邪気を払う力があると言われる菖蒲(しょうぶ)を飾って厄払いをしていました。
これが日本に伝わったことが、元々の由来と言われています。
また、それより前から、日本には「五月忌み」と言う、若い女性たちが家にこもって心身を清める儀式のような習慣がありました。
この二つの風習がミックスされ、女性たちがこもる家の屋根に菖蒲がしかれたりするようになったのです。
つまり、この時代の「こどもの日」の主役は、女性でした。
そこからさらに時代が進み、武士が社会の中心になると、菖蒲の葉の先っぽが剣の形に似ていることなどから、カブトを飾ったり、菖蒲湯に入ったりするようになり、「こどもの日」の主役が男の子になったのです。
また、「菖蒲」=「勝負」=男の子という語呂合わせからも、男の子の祭りになったとも言われています。
鯉のぼりをあげるようになったのは、江戸時代と言われています。
この時代には、武士が活躍していたため、自然と、男の子の成長を祈るものとなっていったのです。
この頃は、医療や衛生が発達しておらず、産まれた赤ちゃんも大きくならないうちに亡くなってしまうことが多くありました。
そのため、赤ちゃんが元気に育つようにお祈りするため、鯉のぼりをあげたと言われています。
始まりは将軍です。将軍家に男の子が産まれると、家紋のついた幟を立ててお祝いをする習慣がありました。
これが次第に武士の家にも広がり、男の子が産まれた印として、また元気に育つよう祈りを込めて、幟を立てるようになりました。
これが、町民にも広がり、そこで、幟に鯉を描くようになったのです。
なぜ鯉なのか不思議ですが、鯉は汚れた水の中でもたくましく生きるのが特徴です。
鯉のように、どんな環境でも立派に成長するようにとの願いが込められていると言われています。
こどもの日のプレゼント普及は核家族化が原因?
こどもの日のプレゼントは、カブトや鯉のぼりなどの飾り物がコンパクト化してきている事と核家族化が大きな要因になっている気がします。
飾り物のコンパクト化の場合マンションなどに住むと、どうしてもコンパクトサイズの飾りを選びがちです。
金額的にもコンパクトな飾りが多い(もちろん小さくても高価な物はありますが)ので、それを補う形でこどもの日にプレゼントしているようです。
大人からすると金額的に浮くのがメリットとなり、子供達からすると好きなものがもらえる事がメリットになるわけです。
核家族化の場合は核家族の子供達は、祖父母と疎遠になりがちです。
なかなか会う事が出来ない代わりにこどもの日には孫たちにプレゼントをあげたくなるそうです。
祖父母にとってみるとプレゼントを上げる事が孫に会う口実になると言うメリットになりますね。
こどもの日のプレゼントまとめ
こどもの日のプレゼントは12歳ごろまでの家庭が多く、レゴなどの知育玩具が人気のプレゼントとなっています。
小学生の子供にはゲーム・洋服・文房具などをプレゼントが人気です。
こどもの日の飾り物がコンパクト化して、プレゼントが普及してきたようです。
飾り物を毎年飾るのは、少し億劫でもありますが、子どもに対する「あなたたちのことが大切なんだよ。」って気持ちも伝えられる気がします。
毎年こどもの日を感謝して迎えたいですね。