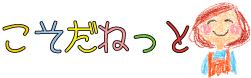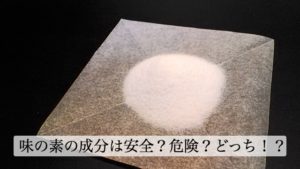4連休明け5月~6月にかけて耳にし始めるのが五月病です。
この五月病、ひと昔は大人に対しての病気と言われていましたが、最近では子供が五月病にかかるケースが急増していて、大人だけの病気ではなくなってきています。
そんな「子どもの五月病」について調べてみました。
五月病になった子どもの症状
五月病とは、医学的には「適応障がい」「抑うつ状態」と診断される病気です。
精神的または身体的なストレスや疲れによって心身に大きな負荷がかかり、脳がうまく働かなくなった状態のことを五月病と言います。
症状が五月のゴールデンウィーク明け頃からでることが多いことが五月病の名前の由来です。
幼稚園の教諭をしていた頃、五月病の症状が出た子がいました。
入園、そしてすぐ弟も産まれて、その子の心は乱れっぱなしで、
登園時には泣きわめいて「幼稚園行かない、お母さんといる」と叫んでいました。
お母さんも、毎朝泣いていました。
でも、そこでお母さんは負けずに、その子にきちんと向き合って
その子との時間を大切にしました。
すると、いつしかしっかり新しい環境になじみ、
自信に満ちた表情で園生活を送れるようになりました。
弟にもすごく優しいお姉ちゃんになりましたよ。
あのときお母さんが、「じゃあもうしらない!!勝手にしなさい!」なんて毎日叱っていたら、
今ごろ、どんな風に成長しているのか・・
きっと何事にも消極的だったり、自己肯定感が低かったりするのだと思います。
子供の五月病は少子化が関係していた?
五月病は近年、大人だけでなく子供も患い、その患者数は更に急増している傾向にあります。
ひと昔前に「五月病」と言う言葉が、ある医師から誕生し、その時は大人に対しての診断が多かったのですが、近年では子供も同じ症状を訴えその患者数は急増しています。
ひと昔前は考えられなかった子供の五月病…。
なぜ今頃になって子供の五月病が急増しているのでしょうか。
それは…少子化が関係しているからです。
少子化になると親や先生のような大人が子供を過度に干渉する傾向になってしまいます。
そのため、子どもはほぼ大人の言いなり状態なので自立できなくて、子供本来の柔軟な思考さえも失われつつあるのです。
[子供に必要なモード変換]
・年度初めの四月に緊張しながら様々な事に慣れる努力をする⇒やる気モード
・ゴールデンウィークで緊張と疲れた体を癒す⇒休みモード
・ゴールデンウィーク明け(五月)通常の生活に戻る(また慣れる努力の始まり)⇒やる気モード
※このモード変換が柔軟に行えなくなってしまうと言うわけです。
これを見て分かるように、特に人一倍頑張ってしまう子・まじめな子は適当な事ができないため、柔軟な切り替えが難しいので、五月病を患いやすく症状が重くなる可能性があります。
子供の五月病の対策
五月病は子供も急増していて、最悪の場合は登校拒否と言う結果になってしまいます。
そのような事にならないために、子供の五月病の対策を知っておく必要があります。
五月病を患いやすい子供の特徴としては頑張りすぎてしまう子、まじめな子です。
頑張りすぎてしまう子は心に不安を持っている子が多いので、頑張りを認めてあげて、これ以上の頑張りは不要である事を伝えると安心します。
まじめな子は、インドア派の子が多く意外性とは縁遠いので、アウトドアや外遊びをさせると臨機応変の訓練になって、柔軟な思考になりやすいです。
五月病を患いやすい子は、基本的に環境の変化に弱い傾向がありますので、五月病の対策としては臨機応変できるようになれば根本的な改善が可能となります。
また、五月はきりのいい時期だからと、塾や習い事を始めようと考える家庭も多いと思います。
たしかに、スタートするにはきりがいいように思えますが、
新しいことが重なると、詰め込みすぎになってしまい
子どもにはかなりの負担になりますよ。
しっかり子どもの声も聞いてあげてください。
子どもたちも疲れています
新一年生も、それぞれ進級した子どもたちも、この時期、緊張からくる疲れがピークに達する時期です。
たしかに、思い返せば、我が子たちもすぐ怒ったり、泣いたり、感情が安定しなかったことがありました。
それはそうですよね、大人だって新しい環境は疲れます。
子どもならなおのこと、ストレスを感じるはずです。
もし、自分の子どもに、五月病かも、と思われる症状が出たらどうすればいいでしょうか。
一番は、何に対しても無理はさせないことです。
ついつい「○年生になったんだからがんばりなさい!」などと言ってしまいそうになりますが、それはぐっと我慢してください。
また、子どもが愚痴を言いたいときには、最後まで話を聞いてあげましょう。
アドバイスをもらいたいわけではないのです。
「そうだよね。疲れちゃうよね。」って、ただ共感して欲しいのです。
子供の五月病まとめ
近年、五月病は大人だけでなく子供も患っています。
その患者数は急増しています。
その理由としては少子化が関係していると思われ、大人の過度の干渉によって子供の自立思考・柔軟な思考が失われつつあります。
そのため、やる気モードや休みモードを変換する事が困難になり五月病を発症してしまうようです。
五月病は、頑張り屋さんやまじめな子ほど柔軟な思考にはなれずに患いやすいようです。
この対策としては、臨機応変が必要となる外遊びなどがおすすめです。
誰だって、自分の子どもの弱い姿はみたくないし、愚痴だって聞きたくないです。
でも、この時期親子で踏ん張れば、子どもは見違えて成長するし、親子の関係も深まります。
あせらず、ゆっくり見守ってあげましょう。