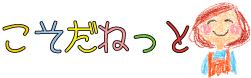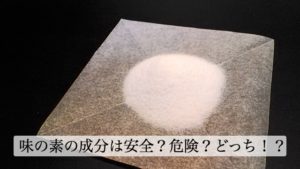三姉妹だった我が家のひな祭りの3月3日の夜は、ご馳走でいっぱいだった記憶があります。
2月中旬からおばあちゃんが買ってくれた7段のひな人形を一緒に飾って、ひな祭りの日を今か今かと待ったものです。
おやつには、ひなあられを食べて、夕食はちらし寿司とお吸い物を食べていました。
今ではかわいくて、いろいろなメニューがありますが、1つ1つに意味があるのでそれをご紹介したいと思います。
ちらし寿司
ひなまつり=ちらし寿司というイメージが強いと思いますが、ちらし寿司にも意味がありました。
蓮根は、穴がたくさんあいていることから、見通しがよい将来でありますようにという意味があります。
えびは、腰が曲がるまで健康で長生きしますようにという意味があります。
豆は、健康でまめ(豆)に働けますようにという意味があります。
また、寿司という漢字は「ことぶき(寿)」を「つかさど(司)る」と書きます。
なので、お祝いの席では縁起がいいとしてお客様には喜ばれる料理ともいえるでしょう。
最近では、オーストラリアでも日本の食材が簡単に手に入るようになったので、「ちらし寿司の素」を使って、簡単に手際よく簡単に作れるようになりました。
これが手に入らない時代は、蓮根探しから始めるので苦労しました。
今でも蓮根はなかなか普通のスーパーでは売っていません。
ちらし寿司ケーキ
今日はひな祭りなので
— あまね🎨🍰🐨 (@_amane_hikaru_) March 3, 2022
ちらし寿司ケーキ作りました!🎎✨#ひな祭り #桃の節句 pic.twitter.com/VgomcYB9K5
我が家では、ちらし寿司ケーキとして、ケーキ型に入れて、刺身をバラの形にしたり、にんじんを桜に、
きゅうりを葉っぱに見立てたりして飾ります。
こどもがまだ小さい時は、じゃこなどの魚と一緒にやわらかいご飯をクッキーの型などに入れます。
きゅうりやにんじん、ブロッコリーなどを飾ると色とりどりでかわいいです。
芽を出す野菜も縁起がよいので、アスパラガスもいいかもしれませんね。
手まり寿司
少しでもひな祭り気分を味わいたくて、今朝は簡単3種の手まり寿司 pic.twitter.com/a35N9FsXND
— 〒 (@___365likfe) March 2, 2023
また乳幼児も食べやすい手まり寿司も、最近は海外でも好評です。
難しそうに見えますが、ラップを使って握るとカンタンにできます。
手まり寿司は、ちらし寿司のように取り分ける必要がないので、ひなまつりだけでなく、パーティーには最適ですね。
貝のお吸い物
子供のころから、アサリやハマグリなどの貝類が大好きだったので、ひなまつりでの貝のお吸い物はおかわりするほどでした。
2枚貝は昔から女性の貞操、幸せな結婚や長続きする愛などの象徴とされていて、とても縁起がよいです。
通常2枚貝は、対になっている貝殻としかぴったり合いません。
なので、相性がぴったりの相手と結婚し、幸せな人生を歩めるようにと、お祝いの席では好んで食べることが多いでしょう。
また、貝のお吸い物の代表として多いハマグリは、旬が初春にあたります。
ということもあり、ひなまつりのお吸い物はハマグリが入っていることが多いのです。
ハマグリは鉄分、ビタミンB1・B2、カルシウム、マグネシウム、亜鉛、カリウム、ナトリウムなどの栄養素も充実しています。
子供だけでなく出産したばかりで貧血気味のママにも嬉しい食材です。
ひなあられ
ひなあられは、ひな祭りの代表的なおやつですよね。
昔からの栄養源であるでんぷんを使用してでした。
ひなあられは多くの場合、白、緑、赤、黄の4色です。
4つの色で作られているのは以下のように、4つの季節をイメージしているといわれています。
白=冬
緑=春
赤=夏
黄=秋
4つの季節を通して1年中、娘が幸せで健康に過ごせますように、という親の願いがこめられているのです。
関東育ちの私は、甘い味のひなあられでした。
なので、ひなあられと言えば甘いものと思っていましたが、関西の友人から聞いたところ、どうも違うようです。
関西では、しょっぱくて少し大きめなのが「ひなあられ」だそうです。
狭い日本で西と東の味も形も違い、驚きました。
少し手間がかかりますが、甘さや塩気が気になる乳幼児の娘さんには、切り餅やもち米を揚げて手作りもいいでしょう。
ひな祭りの由来とは?
「日本では、農耕儀礼の払えの行事として、3月の初めに海や山へ出て、1日を過ごし、身の汚れを洗い流す習慣がありました。
これは、田植えの始まりの季節に、田の神を迎えるためのもので、この時に、紙を人形に切り抜いた人形をつくり、それで体をなでて、汚れを落としたのちに、海や川に流していました。」
子供に伝えたい年中行事」
ひな祭りは、田植えの神様を迎える為のもので人形を流す行事でした。
現在でも鳥取県の因幡地方や和歌山県の吉野川や紀ノ川の流し雛は有名です。
それが時代とともに、(人口の増加など)川に流すのが難しくなっていきました。
また、技術の進歩とともに、人形が豪華になっていきました。
その豪華な人形を流してしまうのは、もったいないと言う事で、今の様な観賞用になっていったと言われています。
ひな人形は、時代とともに豪華になっていきますが、人の代わりという意味合いは今でも残っています。
災いを人形に代わってもらうという意味合いです。
そのため、江戸時代には嫁入り道具の中にひな人形を入れるようになったそうです。
中国では昔、3月3日を上巳(じょうし)の節句といい(3月の初めの巳の日)けがれをはらうために、お酒を飲んだりする行事がありました。
この行事が、日本に伝わり次第に合わさって、同じ日になったのではないか?と言われています。
上巳の節句は、桃の節句や弥生の節句とも呼ばれています。
関連記事桃の節句にお祝いをいただきました。 お返しは何を選ぶ?おすすめのグッズは?
ひな祭りの食べ物まとめ
ひな祭りではハマグリやえび、れんこんや豆など、縁起のいい食材でお客様をお迎えしたいものです。
またまだ小さい子供でも、目で口で季節を味わえる、こういった日本文化は大切に次の世代に引き継いでいこうと思います。
私の場合、日本の母が孫へとオーストラリアまでひな人形を送ってくれました。
しかし、オーストラリアの厳しい税関に引っかかり、ひな人形を飾る台だけしか届きませんでした。
なので、娘の初めてのひな祭りは、残念ながら台だけでした。
でも、その台に娘が座って遊んでいたのも良い思い出になりました。
こういう懐かしい思い出は、いつか娘がお嫁に行くに、ひな人形と一緒に持たせてあげたいと思います。