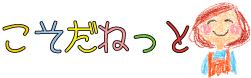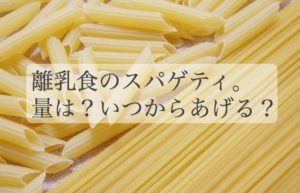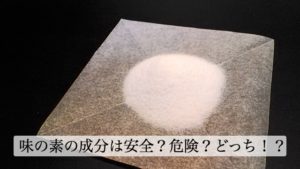子どもってほんとにあっという間に成長しますよね。
やっと歩けるようになったー!!と思ったら
ママって言ってくれたー!!って感動して。
ほんとにかわいい愛しの我が子!
なーんて思ったのもつかの間で、2歳になると始まるのがイヤイヤ期。
これ…成長に欠かせないのは分かるんですけど、本当にイライラさせられる厄介なやつです。
だって、何を言っても「イヤ!イヤ!」と、言うことを聞かずあげくには大声で泣き出してしまうのだから・・・
ホント、たまりません。
だいたいイヤイヤ期って言い方何よ…‼
そもそも何がイヤなのよ‼
我が家では一年前にイヤイヤ期を脱出しましたが、2歳のイヤイヤ期真っ只中に悩むママの大変なお気持ち、お察しします。
ずっと続くわけではないけれど、なるべくなら上手に乗りこえたいですよね。
しょせんはこの世に産まれてたった2年の子どもです!
ここは大人として、手のひらで転がしちゃいましょう。
イライラするからと言って子ども相手にブチ切れていてはダメですよね。
2歳児には2歳児の叱り方があります。
今回は、そんなイヤイヤ期の2歳児の対処方法がテーマです。
目次
イヤイヤ期は反抗期?どんなことがおきる?
- なんでも「イヤイヤ~」と言われる
- なんでも自分でやりたがる
- 暴れる
- 気まぐれ
- 反抗的になる
- 寝かしつけに時間がかかる
イヤイヤ期とは、「第一次反抗期」のことです。
子供が、初めて自己主張をし始める時期の事です。
まだ上手くしゃべれない時期の子供が、“自己主張”をする時に、簡単な『イヤ』という言葉を使う事が多いので一般的にイヤイヤ期と呼ばれています。
一般的には自我が芽生える2歳ごろから始まって、3歳ごろには落ち着いてくると言われています。
かわいいかわいいで育ててた子どもが2歳になって、初めて子育ての難しさを感じる方も多いと思います。
「魔の二歳児」とも言われていて、子育ての中で
一番ママが困る時期かもしれません。
早い子では1歳からイヤイヤ期が始まります。
今までは受け身で、親に散歩に連れてもらったり、ご飯も食べさせてもらったりでした。
その子供が、だんだんと自己主張が始まる時期です。
自分でやりたいことがわかるようになるという、成長の証です。
でも、親としては受け身だった子供が、少しづつ自己主張し始めると、普段のリズムと違うので戸惑います。
すこし、やわらかく書きましたが、私の場合はイライラが止まりませんでした。
1年間ママをしてきたので、頭の中では、もう1日のスケジュールが決まっています。
- 朝10時には散歩に行って、
- 10分で公園に着き、
- 30分遊んで10分で帰ってくる。
というスケジュールがあるのに、イヤイヤ期になるとスケジュールどおりには行きません。
上記のたった3行のスケジュールが、イヤイヤ期になるとこうなります。汗
- まずは、靴下が気に入らないと、靴下を履き替えます。
- その後、自分で靴を履きたいと、時間をかけてやっと履いた。
- と思ったら、いつもは乗るベビーカーを押したがります。
- ベビーカーに乗れば10分の公園の道、歩き始めたばかりの娘はベビーカーを押して倍以上の時間をかけ、やっと公園に到着します。
- やれやれ、と思ったのもつかの間、ブランコには乗らず、テディーベアをのせて押します。
- その後は砂場で砂だらけ。
- では帰ろう、と支度を始めると今度は自分がブランコに乗る番だと帰ろうとしません。
- やっと帰れることになったら、また倍以上の時間をかけて帰宅します。
- そして、帰ってきた昼ごはんは自分で食べたがる。
- ごはんの半分は床に落ち、半分は服を汚し、ほとんど食べず、昼寝・・・
ママの家事は山積みで、堪忍袋はもう、いっぱいいっぱいです・・・
ただ、まれにイヤイヤ期がない子もいます。
元々の性格があっさりしていたり、皆と同じ時期にイヤイヤ期にならない子供もいます。
成長はその子供によって違いますので、一般的に言われる2歳にイヤイヤ期にならない場合もまれにあります。
遅れてイヤイヤ期になるのかどうかもその子によって違います。
もしも、何か心配なことがあったら市町村の保健婦さんに相談してみて下さいね。
イヤイヤ期中の2歳児の叱り方はこうです
子どものイヤイヤ期の大変な所はなんと言っても突然訪れる事です。
「お靴反対だよ」なんて靴にさわろうものなら
「ヤダー!!!!!」
って靴を投げてしまう…
こんなときに「こら!お靴投げたらダメでしょ!」
なんて言ったら大体大泣きで収拾がつかなくなりますね…
思い出すだけで恐ろしい…
子どもの気持ちになって考えると「自分一人で靴をはきたかったのにママがさわって邪魔したからとっても嫌な気持ちになった」
という解釈が出来ると思います。
まずは100歩譲って大人の対応。
子どもが上手く言葉に出来なかった嫌な気持ちを代わりに口に出してあげて、心を整理してあげましょう。
「一人でお靴を履きたかったんだね。ママが邪魔しちゃったから嫌な気持ちになっちゃったんだね?」
自分の気持ちを整理出来れば子どもながらに少し冷静になります。
そこで、ママの伝えたいことをお話しましょう。
「お靴は投げたらダメだよね」
2歳の子どもは自分でうまく言葉に出来ない感情があると、物に当たったり噛みついたりという行動出てきます。
決して困らせてやろうなんて悪意はないので、良くないことをしてしまったときはその都度その都度繰り返し言い聞かせるように注意していきます。
イヤイヤ期に寝ない時の対処法
イヤイヤ期になると、お昼寝をしなくなる子供が多いです。
お昼寝してくれないと、ママはホッとする時間がなくてつらいですよね。
お昼寝の寝かしつけに1時間もかかって、でも寝ない。(泣)
・・・なんて時はどうすればよいのでしょうか。
また、夜もお布団に入ってもなかなか寝ない、という話をよく聞きます。
そんな時もどうすればよいのでしょうか?
早寝・早起きを徹底!
昨晩、眠るのが遅くとても、朝7時半までには必ず起こしましょう。
夜は5時45分ごろにはお布団に入れるようにすると良いですね。
お昼寝をしない場合は、夜、もっと早く寝てしまう事もあります。
基本の早寝・早起きのペースは乱さないようにしましょう。
夕飯は簡単なものか、早めに作っておく、入浴の準備も早めにしておく
お昼寝しない子供はだいたい夕方になると
眠くなってきてご機嫌がとっても悪くなります。
その相手をしながら夕飯の用意や入浴の準備をするのは大変です。
子供の機嫌が良いうちに準備しておきましょう。
できるだけ外で遊ばせる
外で太陽の光をしっかり浴びるて体を動かしてあげると、
お昼寝してくれるか、夜も、とっても早く寝てくれます。
ママも疲れてしまいますが、子供の体も丈夫になって良いですね♪
夜なかなか寝ない時は諦める。
早く寝てほしい時に寝てくれない時はいっその事諦めましょう。
それでも、10時半以降になると、子供も自然に眠くなってきます。
たまには夜更かししても仕方ありません。
そのかわり、翌朝は早めに起こしましょう。
イヤイヤ期の子供の行動と私の対処法
靴下が気に入らない→まずは認めてあげる。
洗濯が増えるし、時間も倍以上かかります。
でも、自分がそうだったら、やっぱり履き替えたいですよね。
だから我が家では「わかった。じゃあ、はんぶんこ!」という言葉を合図にしてます。
で、1足はママが手伝って、1足は子供が自分で履き替えをするというように、自分でできるようになるまでお手伝いしていました。
ママに気持ちを分かってもらえるって子供もうれしいものだと思います。
ベビーカーに乗らず歩く→とにかくつきあう。
ベビーカーに乗ってくれればママのペースで歩けるし、時間もかかりません。
でも、いつかは自分で歩く日が来るのです。
だから、練習だと思ってとにかく付き合いました。
ママも楽しめるように、一緒に道草をして野花を摘んだり、せみの抜け殻探したりと、公園までゆっくり時間をかけました。
そして、手をつないで公園に行く時間、何度も「ママと手をつないで一緒に歩いてくれて、とっても幸せ」と気持ちを伝えていました。
この頃から、動きやすさを重視に、ベビーカーの変わりに抱っこ紐を持参しました。
ブランコにテディーベアを乗せる→したいようにさせる。
他の子供が待っているならともかく、誰もいないなら、しばらく自分のしたいようにさせることも大切だと思い、公園の中ではなるべくしたいようにさせていました。
ブランコに飽きて、テディーベアと砂だらけになっても、「ぬいぐるみと服は洗えばいい」と諦め、したいことをさせていました。
もちろん、お友達を叩いたり、順番を守れなかったら、公園のルールを教えます。
でも、なるべく自主的に行動できるよう、公園では「○○して遊びなさい」と言わないようにしました。
公園から帰ろうとしない→ 強い口調で叱る
子供が遊びたいという気持ちは大切にしたいですよね。
でも十分遊んだ後、お昼ご飯やお昼寝の時間があるので、なるべくスケジュールどおりに動きたいのも事実です。
だから、なるべく事前に「あと10回ブランコ押したら帰ろうね」と告知しておきます。
そして、10回押してブランコが自然にとまっても帰ろうとしなかったら叱るようにしました。
この時、感情的になり過ぎないように注意して、強い口調で話します。
「ママとお約束したよね。お約束破られたらママは悲しい気持ちになるんだよ。」とか
「せっかくママが一生懸命作ったお昼ご飯、どうしたらいいの?食べないで捨てちゃうの?」などと注意していました。
分かってくれたら「ママとのお約束守ってくれてうれしい!」や
「ママの気持ち分かってくれてありがとう」と大げさにほめたりもしました。
自分で食べたがる→気をそらしながら付き合う
もちろん、自立することは大切ですし、誇らしいことだと頭では分かっています。
しかし、やはり食事は服や床ではなく胃に届けたいというのは親心だと思います。
だから、うちでは子供用スプーンをママと子供と2つ用意しました。
子供は自分で食べている気分が味わえます。
また、ママは子供が遊び始めたら、こっそり唇をスプーンでトントンって触り口が開くのを待って、食事を与えられます。
昼寝→たまには一緒に寝てしまう
スキンシップを大切に。
イヤイヤ期でストレスいっぱいのママは、子供が昼寝している間くらいは自分の時間を持ちたいものです。
でも、睡眠ってストレス減少にもなるのです。
またスキンシップは言葉以上に子供を落ちつかせます。
安心な感を与え、反抗も少なくなるかもしれません。
だから、たまには一緒に昼寝してしまうという技もありなのです。
2歳児も頑張っているのです
だけど、忙しい時間に子どもがちょっとしたことで癇癪をおこしたら、正直ママの方が「あー、もうやだ…」ってなっちゃいます。
靴が反対なのを教えてあげたのはママの優しさの現れですよね。
一方、子どもの方からすると「自分でやろうと思った。ひとりで出来てママはビックリするはずだった。」
・・・なんとも切ないすれ違いです。
靴が右左反対なんて…
シャツが後ろ前逆なんて…
ママは気持ちが悪いかもしれません。
最初から右左、後ろ前しっかり教えておきたい、と思うのが大人の普通の感覚だと思います。
しかし、2歳児の場合、正確に出来たということは実は重要ではないことがわかっています。
それよりも、2歳児は「自分ひとりで出来た」という、達成感を求めています。
何でも一人でやりたがって、逆に時間がかかったり手間が増えたりしますが、大切な成長期としてじっと耐え…いやいやっ、見守ってあげたいですね!
完璧な親などいないのだから気楽にいきましょう!
- イヤイヤ期とは「第一次反抗期」と呼ばれていて、子供がはじめて“自己主張”をはじめだす時期の事。
- イヤイヤ期の特徴は“なんでも自分でやりたい”“「イヤイヤ」言って横になってジタバタ暴れる”
- イヤイヤ期は一般的に2歳ごろからはじまり、3歳ごろ落ち着く。
- まれにイヤイヤ期のない子供もいる。
- 寝ない時の対処法は、早寝早起きのリズムを崩さないように。
- 夜更かししても翌朝は早く起こす。
- 夕飯は簡単なものかあらかじめ準備をしておく。
- 入浴の準備も早くしておくとベスト。
今まさに魔の2歳児と戦っている人、これからイヤイヤ期が心配な人もいるかと思います。
ただ、「魔の2歳児」は誰もが通る道です。
大人としては毎日「イヤイヤ」言われたらイライラしてしまい、どうしていいか分からなくなるかもしれません。
しかし、このイヤイヤ期こそ子供の成長の証であること、ずっと続くわけではなく終わりがくることをどうか忘れないでください。
時には、お母さんお父さんのストレス発散も心がげてみてくださいね。
別ページ『子育てがつらいと思ったらすぐに試してほしい対処法を先輩ママが伝授』も是非ご覧になってください。
イヤイヤ期の助けになると思います。
私も子育てに悩んだ時は沢山ある育児書を端から端まで読みました。
育児書を読んでいていつも思ったのは、「こんなに優しく理想のママのように子どもと接することが出来たら
悩んで育児書なんて読まなくて済むんだけどな…」
こーするのが良いと分かってはいても上手に対応出来ないのは、お母さんも人間だから。
育児書と同じように対応してみても上手くいかないのは、子どももみんな違うから。母としてだけじゃなく、妻として、社会人として、色んな悩みもあると思います。
私も心に余裕がもてない時は子育ても上手くいかなくって
自己嫌悪になってしまうことも良くありました。
イヤイヤ期の子育てに煮詰まった時には、「もう深く考えるのは辞める。」これが一番です。
なるようになる!
そう思って、少し肩の荷を降ろすことも大切ですね。